


更新 25.8.21





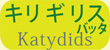
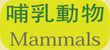

 |
||||||||||||||||||||||
 |
 |
|||||||||||||||||||||
|
|
更新 25.8.21
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
 |
 |
 |
 |
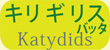 |
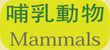 |
|||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商用・WEBサイト・展示・研究・報道などに、音声や写真の使用を希望される場合は |
||
|
音声や画像は著作権法で保護されたUNSの著作物です Copyright UEDA NATURE SOUND All Rights Reserved
|